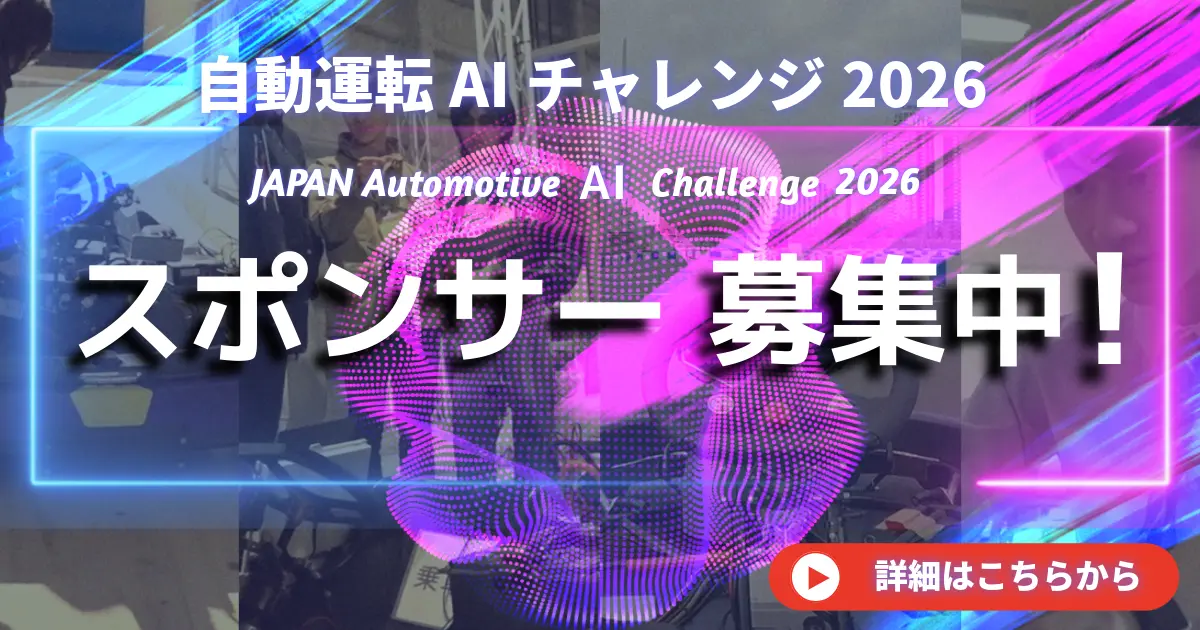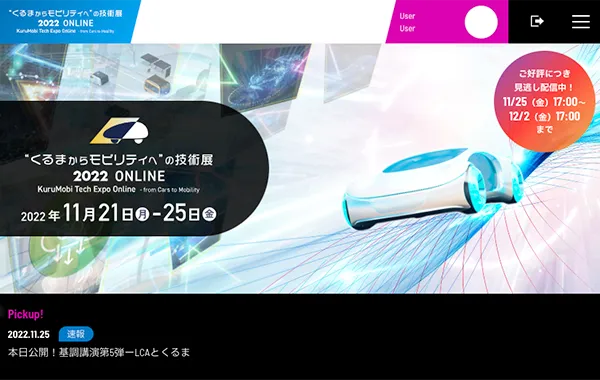News
- 【閉幕のお知らせ】ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!
- 2025/12/19
- ニュース
移動を超え、人々の生活や社会そのものを変革する体験価値の創造
—それが今日のモビリティ革命の本質です。
自動車産業の枠を超え、テクノロジー企業、サービスプロバイダー、スタートアップから大手まで、すべてのイノベーターの目がモビリティの再定義に向けられています。
オンラインで培ってきた知見を、初の実体験へと昇華させる本イベントは、業界の垣根を越えた出会いと協業を促進し、次世代モビリティ市場における貴社のポジショニングを確立する絶好の機会です。
ここに集うビジョナリーたちとともに、技術とアイデアを融合させることで、移動体験の未来図を描き、具体的なビジネス成果を生み出すエコシステムの一員となりませんか。
モビリティの再定義が進む今、その潮流の中心にいるかどうかが、ビジネスの明暗を分ける時代がやってきています。
この歴史的転換点に、ぜひ貴社も未来のモビリティを共創するプレーヤーとしてご参画ください。
東京国際フォーラムでのオンサイトセッションと、いつでもどこでも視聴可能なオンラインセッションを組み合わせた、ハイブリッド形式のプログラムを展開。SDV、自動運転、AI、モビリティサービス、スマートシティ、エネルギーなど、多岐にわたるテーマを網羅し、自動車メーカー、テクノロジー企業、スタートアップ、行政機関など、業界を代表する多様なプレーヤーが登壇します。技術開発の最前線から社会実装の実例まで、次世代モビリティのあらゆる側面に触れられる、充実のラインナップです。
12月10日(水) 東京国際フォーラム会場にて、
各界のリーダーが未来のテクノロジーについて講演します。

-
9:50〜10:5012月10日(水)
SDV時代のE&Eアーキテクチャ
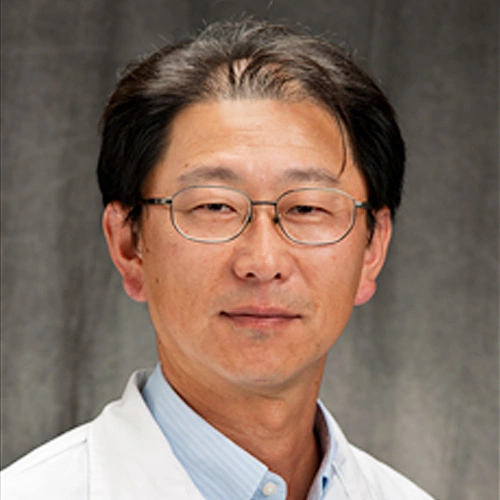
クルマは、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)へと急速に進化を遂げています。
SDVにおいては、顧客ニーズを的確に把握しタイムリーに新しいバリューを届けられるかどうかがクルマの魅力を左右します。
ホンダの考えるSDVを実現するE&Eアーキテクチャの進化について解説します。 -
13:00〜14:0012月10日(水)
うごく、つながる、未来をつくる。

KDDIは、グローバルなコネクティッドカー実績と運用監視の知見を活かし、SDV自動運転車両やAIロボットが拓く未来のモビリティ社会を支えます。
-
17:00〜18:0012月10日(水)
SDVからAI-Defined Vehicleへの変遷と日本が取るべき構え

現在、グローバルのモビリティ業界においてはSoftware-Defined Vehicle、さらにはAI-Defined Vehicleへと変遷を遂げており、AI技術が今まで以上に競争の根幹・分かれ目となってきています。こうしたグローバル最前線の動向を押さえつつ、自動運転・ADAS領域やIVI・コネクテッド領域における最新潮流とそれに基づくインサイト、日本企業が取るべき構えについて講演致します。
11月26日(水)10:00〜 12月19日(金)17:00
各講演の講演時間は約30分です。
-
SDV化の進展や自動運転技術の実装による自動車産業の変革と政府の取組

SDV化の進展や自動運転技術の実装により、自動車が新たな価値やサービスを提供し、それに伴い業界構造や自動車の開発プロセス、重要技術など、自動車産業を取り巻く環境は大きく変化する見込みです。このような中で、政府の戦略や今後の見通しについてお話しします。
-
SDVーその本当の意味

SDVという言葉が多く語られるようになって2年以上が経ちます。ソフトウェア定義型車両という言葉で一般のメディアにも現れています。一方、SDVとは?という話になると、業界人であれ、「様々な定義がありますね」とぼやかされる事が多いです。本講演では、SDVの本当の意味は何なのか、それを踏まえてどのようなアプローチが必須なのかについて議論します。
-
自動運転の民主化 〜 AutowareとEnd-to-Endの最前線 〜

オープンソースAutowareを基盤に広がる自動運転の民主化と、次世代の潮流となるEnd-to-End技術の最新動向・実践知を紹介します。
-
自動運転に向けたフィジカル基盤モデルの現在地

昨今、自動運転だけでなく多様な分野で注目される視覚・言語・行動を統合処理するフィジカル基盤モデル。本講演では、チューリングの最新の開発事例を交え、その進展と現状をわかりやすく紹介します。
-
自動運転によるモビリティサービス実現へ向けた取り組み

将来の移動手段として、運転手が不要な、レベル4の自動運転によるモビリティサービスへの期待が高まっていますが、その実現にあたっては安全面、サービス運営や事業性、ユーザの受容性など様々な課題が挙げられています。これらの課題に向けた、日産自動車における開発、実証の取り組みを紹介します。
-
持続可能な地域創造のための移動の課題とシェア乗りの新たな可能性

日本が今後成長を続けるためには、観光地を含めた地域の魅力を高め、持続可能な形で運営する必要があります。その中でもそれらを繋ぐ必要不可欠な“移動”における現状の課題とシェア乗り(相乗り・乗合)などのサービスを通じての新たな可能性のお話をします。
-
DXによる飲んだら運転できない社会の実現へ

飲酒運転による違反や痛ましい事故をゼロにしたい。70年以上培われた自動車用鍵技術と最新のデジタルキーが融合し、“飲んだらエンジンがかからない仕組み”を通じて、DXを活用した安全・安心な社会の実現を目指します。
-
MaaSによる社会課題解決への挑戦
〜 オンデマンドモビリティサービス・医療MaaS・行政MaaS最前線 〜
日本の社会課題(移動困難者の増加、医療・運転手不足等)は、急激に深刻化しています。モビリティとシステム・データの組み合わせで、どう解決するか。現場で、自治体様や住民の声を聞きながら日々奮闘している「MaaS最前線」をご紹介します。
-
「移動×データ」で実現するモビリティの未来

NTTドコモが提供する「いつ、どこに、どんな人がいるのか」を24時間365日推計するモバイル空間統計技術等を活用した社会課題解決、AI渋滞予測などの社会実装例を紹介します。
-
DER活用に関する当社の取り組みについて(EVリソースの電力系統での活用)

当社はカーボンニュートラルの機運を受け普及するEVをDERとして電力系統で活用することで、系統の課題解決に貢献することを目的に、海外電力SMUD・HECOと協働しDER活用に関する制御方法の調査に取り組みます。
-
商用EVの普及に向けた急速充電器技術の紹介

運輸事業者(路線バス、配送トラック)の電動車両は、乗用車タイプの電動車に比べ大容量の蓄電池を搭載しており、事業所内での基礎充電においても複数台の急速充電器が必要となります。この課題を解決する新たなコンセプトの急速充電器技術を紹介します。
-
カーボンニュートラルの取組みと循環型社会へのチャレンジ

トヨタ自動車はトヨタ環境チャレンジ2050に基づき、カーボンニュートラル(CN)とサーキュラーエコノミー(CE)の実現に向けた取組みを推進しています。本講演では、CO₂削減や資源循環に関する取組みを紹介します。
-
水素社会実現に向けた水素ステーションへの取り組み

エネルギーとしての「水素」を取り巻く状況(日本政府の政策を含む)、及び水素社会実現に向けて当社が行う水素ステーションへの取組みを説明します。
Networking Party
立食形式パーティーを通して
講演者・出展社・来場者との交流を図ることができます。
- 参加
- 無料
- 場所
- 東京国際フォーラム D5ホール
- 時間
- 18:15~19:30
将来のモビリティ社会の実現を支えるあらゆるソリューション・製品をはじめ、
クルマのネクストステージに向けて必要な技術分野を変革するテクノロジーを紹介します。
出展社セミナー情報
出展社によるセミナーを実施します。
新技術領域に求められる課題や開発手法、製品技術等について出展社が持つ事例も交え発表します。
12月10日 リアルイベント会場

- 会 期
- 2025年12月10日(水)
- 開催時間
-
9:00 ~ 19:30
- 会 場
-
東京国際フォーラム D1・D5・D7ホール
会場HPはこちら〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
自動車技術会 関連イベント
アーカイブ
Supported by